障がい者グループホームでのショートステイとは?|どう利用する?目的や流れを解説
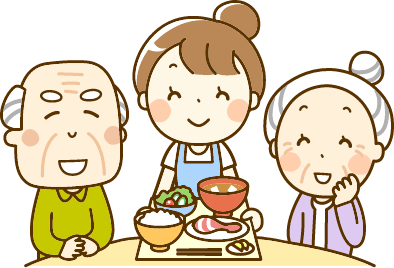
はじめに:ショートステイ(短期入所)って何?
「ショートステイ」とは、障がいのある方が 一時的にグループホームや福祉施設に宿泊して支援を受けるサービス で、主として次のような目的で利用されます。
厚生労働省の障害福祉サービスにおいても、「短期入所(ショートステイ)」 は共同生活援助などと並ぶ給付サービスの一つとして位置づけられています。
利用者が普段は自宅で暮らしていても、介護者(家族・支援者など)の都合、入院、冠婚葬祭、旅行、体調不良、レスパイト(休息)などの理由で、短期間、施設での宿泊・支援を受けるのがショートステイです。
障害福祉の世界では「短期入所」「ショートステイ」がほぼ同義で使われることが多く、障がい児にも成人にも対応する施設があります。
また、ショートステイと似た概念に「日帰り型(=日中一時支援)」があり、宿泊を伴わない支援を提供するものもあります。
ショートステイを利用する目的とメリット
ショートステイを利用する目的・メリットには以下のようなものがあります。
| 目的 | 内容・効果 |
|---|---|
| 家族・支援者のレスパイト(休息) | 常時介護されている方が一時的に休める時間を確保できる。旅行・冠婚葬祭対応など。 |
| 利用者側の暮らしの変化・慣れ | 他の生活環境を経験することで、自立訓練や生活力の維持・向上が期待できる。 |
| 入院・通院など緊急対応 | 入院・通院で自宅が使えない期間に支援の場を確保。 |
| 移行期の試み | グループホーム入居前のお試しや移行段階として利用する。 |
| 災害・緊急避難 | 災害時の避難先として機能するケースも。 |
こうした目的は、施設運営者・福祉課・相談支援専門員と調整しながら利用されます。
利用対象・制限(年齢・障害区分など)
ショートステイは、障害福祉サービスの一部として「一定の利用条件」が定められています。以下、代表的な制限や目安を見ておきましょう。
年齢・年齢制限
・多くの施設で、18歳以上を対象とすることが多いですが、障がい児向けに児童施設でショートステイ対応しているところもあります。
・65歳以上については、介護保険制度移行等で対応が変わるため、自治体ごとの取り扱いになります。
障害支援区分・障害程度
・多くのショートステイ施設では、**障害支援区分1以上(あるいは区分2以上)**が利用条件とされることが一般的です。
・障害が重度で医療的ケア(チューブ・吸引・インスリン注射など)が日常的に必要な方については、受け入れが難しい施設もあります。断られる理由として、他利用者やスタッフへの安全配慮が挙げられます。
サービス提供条件・兼ね合い
・ショートステイ事業所は、併設型/空床利用型/単独型など、施設構造に応じて形態が異なります。
・施設がグループホームと併設している所も多く、空室を活用して短期入所枠を設けるケースがあります。
・定期的な更新許可が必要な制度設計になっている場合があります。
費用・料金の仕組みと注意点
ショートステイの料金構造は、通常のグループホーム入居とは異なる点があります。
料金構造の特徴
・家賃相当の部屋代(居住費)は徴収されないことが通常原則とされています。つまり、ショートステイでは家賃を別途請求されない施設が多いです。
・食費・生活介護・サービス料等が日割りで請求されることが多い。
・長期間(たとえば1か月相当の滞在)を希望する場合は、6~9万円程度の費用になる例もあります。ただし、この金額にはサービス料や生活支援料が含まれ、通常の入居と比較して家賃分が軽い分、総額で少し安めに抑えられる場合があります。
・医療的ケア対応加算や重度対応加算など、特定条件の利用者について追加の報酬・料金が設定されることがあります(令和6年度の報酬改定で、医療的ケア児者受け入れ対応加算が新設)
注意点
・施設によっては最低泊数が定められている
・体調不良等で早期退出する場合は、1泊分の料金がかかることがある
・介護保険との兼ね合いで高齢利用者は対象外扱いになることも
ショートステイの利用手順・流れ
具体的な流れは施設・自治体によって異なりますが、一般的なステップは以下の通りです。
① 相談・問い合わせ
最初に、相談支援専門員や地域福祉課・障がい福祉担当窓口に相談し、ショートステイ希望を伝えます。各市町村区では「障がい福祉サービス事業者一覧」が公開されており、対象施設を探す手がかりになります。
支援内容の案内を見ることでショートステイ対応の可能性も探れます。
② 利用申請・審査
施設に対して申込みを行います。必要書類は以下のようなものが一般的です:
・障害者手帳
・障害福祉サービスの受給者証
・健康状態の情報・主治医の診断書
・緊急連絡先
・生活状況・支援ニーズに関する情報
施設側で、受け入れ可能かどうかの審査を行います(医療的ケア要件、他利用者との調整、安全性の確認など)。
③ 契約・利用条件の確認
契約書を交わし、利用期間・費用・支援内容(生活援助・夜間見守り・通院同行など)を正式に確認します。
④ ショートステイ実施
利用者は施設で宿泊しつつ、日常生活に近い支援を受けます。支援内容には以下が含まれることがあります:
・食事の提供
・入浴・排泄支援
・見守り・夜間見守り
・通院同行
・生活相談・助言
・レクリエーション・交流支援
⑤ 利用後の評価・継続判断
利用後、支援評価を行い、継続利用の可否や改善点を相談支援員・施設と共有します。
ショートステイを使う際の注意点・リスク
・施設が対応できる 医療的ケアの範囲 を必ず確認する
・早期退出 の際の料金や対応
・定員制・予約制 のため使えない期間がある
・利用者の 症状変動 や環境変化により受け入れ拒否される可能性(例:暴言・帰宅願望強い等)
・65歳以上利用者の場合は、介護保険制度優先となる可能性あり
・運営施設では、短期入所(ショートステイ)実施にあたって建築基準法・消防法・設備基準等をクリアする必要があり、開始ハードルが高いという課題もあります。
・一部グループホーム制度上、グループホームには緊急一時宿泊(ショートステイ)併設が義務付けられているとの解説もあります。
まとめ:ショートステイは利用者・家族双方の“ゆとり”をつくる制度
・障がい者グループホームでのショートステイ(短期入所)は、家族の休息や利用者の自立支援、緊急対応など多様な目的で活用できます。
・利用には、障害支援区分・年齢制限・医療対応可否など条件があるため、まずは相談支援専門員や施設へ問い合わせを。
・利用を検討する際は、施設の対応範囲・料金・予約の可否・見学体験を重視し、複数候補で比較するのが安全です。
当サービスでは、難病に対応したグループホームを無料でご紹介しています。医療連携や費用面など、条件に合わせて最適な施設をご提案します。自身の希望するグループホーム探しは『障がい者グループホーム専門紹介サービス』(https://grouphome-senmon-service.com/)にお任せください。利用者様にピッタリあったグループホームを無料でお探しします。