重度の障害がある方に対応したグループホームの支援体制とは? 〜体制・環境・連携が整った安心の暮らしを実現するために〜
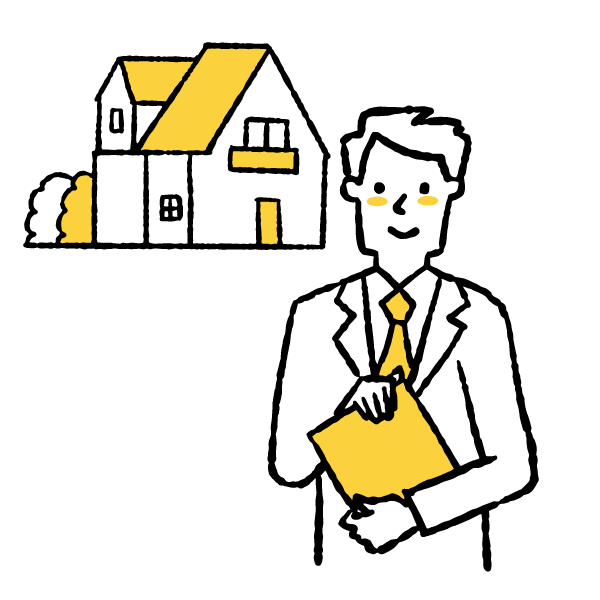
はじめに
重度の障害を抱える方──例えば、身体機能が大きく制限されていたり、知的障害・発達障害に伴って日常生活上高度な支援を必要とする状況──が地域で暮らし続けるためには、ただ「住む場所」があるだけでは十分とは言えません。
そのような方々が安心して暮らすには、しっかりとした支援体制・環境・医療・地域連携が整ったグループホームが不可欠です。この記事では、重度障害の方を対象にした障がい者グループホーム(共同生活援助)でどんな支援体制が必要か、制度の背景から具体的なポイントまでを整理します。
制度的背景:重度障害対応のグループホームが求められる理由
まず制度面から、「なぜ重度障害対応のグループホームが整備されてきたか」を確認しておきましょう。
・厚生労働省は、「障がいの重度化・高齢化」が進んでおり、従来の比較的自立度の高い方を対象としたグループホームだけでは対応困難な状況にあると指摘しています。
・平成30年度には 「日中サービス支援型共同生活援助」 が制度に新設され、重度の障害のある方に対して「日中も含めて常時支援体制を確保」するものとして位置づけられています。
・また「重度障害者支援加算」など、支援体制がより手厚いホームに対して加算が設けられており、支援の質向上を促す制度が整ってきています。
・つまり「重度障害のある方も住み続けられる地域の住まい」をつくるために、グループホームの在り方が変化してきたのです。
このような制度の流れを知った上で、具体的な支援体制・環境・連携の長所を見ていきます。
支援体制の主要な柱
重度障害者対応のグループホームで押さえておきたい支援体制の要素を以下に示します。
1. 人員配置・専門性
・評価基準として「生活支援員・世話人・サービス管理責任者」などの配置が定められており、重度障害対応型では、支援員数の加配や専門研修の修了者配置が条件となることがあります。
・具体的には、「強度行動障害支援者養成研修」「行動援護従業者養成研修」「喀痰吸引等研修(第二号等)」を修了した職員の配置要件が設けられています。
・夜間・休日・深夜など、常時支援が必要なケースでは「宿直専任」「夜間常駐」などの体制を整えている事業所が望ましいです。特に「日中サービス支援型」では日中だけでなく夜間も含めた24時間体制が前提とされています。
2. 個別支援計画・行動支援
・重度障害の方では、単に「食事・排せつ・入浴などを支援する」だけでなく、行動の背景にある理由を理解し、予防的に支援を組むことが大切です。例えば、感情の爆発・他害・自傷・パニックなどを経験する方に対しては「行動関連項目」のスコアが一定以上あることを算定要件とする加算が設けられています。
・支援計画シートという別様式で、行動傾向・環境調整・トリガー・代替行動などを整理し、定期的に見直すことが求められています。
3. 環境整備・設備仕様
・重度障害対応では、「安全・安定・安心」がキーワードです。居室の仕様、防音・安全対策、バリアフリー対応、医療機器対応などが必要になる場合があります。
・また、「24時間支援」の観点から、事業所の住居が単独ではなく、複数棟・サテライト型を含む住居構成を有していることが制度上想定されています。
4. 医療・福祉・地域連携
・重度障害の方は、訪問看護、往診、病院・クリニックとの連携が欠かせません。医療的ケア(吸引・経管栄養・導尿など)が必要な方もおられ、看護師・リハビリ職と連携できることが重要です。
・また、地域移行・通所支援・就労支援・自立生活援助との連携体制を持っているホームは将来の住み替えやライフステージの変化に対応しやすいです。
5. 定期的なモニタリングと家族支援
・重度対応ホームでは「定期モニタリング」「支援評価」「家族会議」などを仕組みとして有しているか確認が必要です。
・家族の高齢化、親亡き後対応が社会課題となっており、ホーム側が家族支援(情報共有・緊急対応・退所後の生活支援)まで視野に入れているかも確認ポイントです。
支援体制を選ぶときのチェックリスト
以下に、重度障害対応のグループホームを選ぶ際に確認すべきチェックポイントをまとめます。
①支援員配置状況
・常勤換算での配置数、夜間・休日対応体制。・強度行動障害・医療ケア研修を修了した職員がいるか。
②専門研修取得状況
・強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修・喀痰吸引等研修の有無。③環境面
・バリアフリー仕様・個室/複数居室の構造。・医療ケア実施可能な設備(喀痰吸引・経管栄養など)が整っているか。
・複数棟・複数住居構成(サテライト型含む)で24時間対応可能か。
④医療・地域連携
・医療機関との連携実績。訪問看護・リハビリ・往診の可否。・日中活動(通所・就労)との連携。
・緊急搬送・急病時対応体制。
⑤個別支援計画の質
・行動支援計画シートの有無。定期見直しの仕組みがあるか。・行動関連項目スコアが高い利用者を対象にした実績があるか。
⑥家族支援・継続支援
・家族との連携・情報共有体制。・退所・住み替え・老後の生活設計への支援体制。
⑦費用・契約条件
・加算取得施設では費用が高めになる可能性も。加算を付けることで支援が手厚い反面、居室定数・利用要件が厳しくなることもあるため、契約書・費用明細を確認。実際の支援体制の“良い事例”から学ぶ
以下に、実際に重度障害者対応をうたうグループホームの支援体制の特徴を紹介します。
・「重度障害者支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」を算定しているホームは、区分6かつ行動関連項目10点以上の方に対して、個別支援計画に基づき対応しており、1日あたり360単位等の加算が可能です。
・制度のガイドラインでは、「日中サービス支援型」においては、短期入所も併設して地域移行・緊急宿泊ニーズにも対応する住まいとして設けられています。
・支援体制を整えたホームは、「夜間巡回」から「夜間常駐」、さらには専門看護師の24時間オンコール体制を取り入れているケースも見られます。
・また、行動支援においては、環境トリガー(刺激・光・音・他者接触)を可視化し、予防的支援を組む事例が、相談支援専門員向けの解説にて紹介されています。
これらの実務的な体制・環境・連携の仕組みが備わっているかが、重度障害対応ホームの“質”を見極める鍵になります。
入居を検討する際の実務的な流れと注意点
重度障害対応のグループホームは、通常のホームよりも検討すべき事項・準備すべき資料が多くなります。以下は全体の流れとその中で注意すべきポイントです。
ステップ1:相談支援専門員・福祉窓口に相談
まずは利用者の現状(医療的ケアの有無・行動特性・現在の生活環境)を整理し、重度障害者対応ホームの紹介を受けましょう。支給決定・受給者証・区分判定が進んでいる方がスムーズに申込できます。
ステップ2:候補ホームの抽出・見学
重度対応と明記されているホームを複数候補に挙げ、見学を申し込みます。先述のチェックリストを用いて、スタッフ配置・医療連携・個別支援計画の有無などを確認。
ステップ3:体験入居・短期入所の活用
可能であれば、ショートステイ(短期入所)や体験入居を利用し、環境との相性を検証します。特に行動変化が起きた際の支援対応を確認できる機会が重要です。
ステップ4:支援会議・契約・入居準備
家族・主治医・相談支援専門員・ホーム職員が集う支援会議で入居の方向性を決定。契約書・支援計画・薬歴・医療的ケア仕様書などを整えた上で入居に進みます。
ステップ5:入居後のフォロー・モニタリング
入居後は定期的な支援計画の見直しと、行動傾向・医療状態・生活リズムのモニタリングが欠かせません。支援の調整によって居住継続が可能です。
注意点
・医療的ケア要件(吸引・栄養管理等)が受け入れ可能か、事前に確認を。
・加算取得ホームは支援水準が高いが、その分入居基準が厳しい・空室が少ないケースあり。
・入居契約時に「退所条件」「医療状態悪化時の対応」「緊急搬送体制」を契約書に明記してもらいましょう。
まとめ
重度障害を持つ方が地域のグループホームで安心して暮らすには、以下の3つが揃っていることが大切です:
・人員・専門性・夜間・休日を含む体制が整っていること
・医療ケア・行動支援・個別支援計画という“支援の設計”がきちんとされていること
・居住環境・設備・地域連携・家族支援など“暮らしを支える安心の構造”が構築されていること
制度上も、「重度障害対応型(加算取得・日中サービス支援型)」という枠組みが用意されており、利用者・家族にとって選択肢が増えてきています。
ただし、すべての事業所が同じレベルで整備されているわけではありません。見学・契約前に支援体制の実態・職員の専門性・医療連携の有無・支援計画の質をしっかり確認することが、安心して暮らし続けるための第一歩です。
当サービスでは、難病に対応したグループホームを無料でご紹介しています。医療連携や費用面など、条件に合わせて最適な施設をご提案します。自身の希望するグループホーム探しは『障がい者グループホーム専門紹介サービス』(https://grouphome-senmon-service.com/)にお任せください。利用者様にピッタリあったグループホームを無料でお探しします。